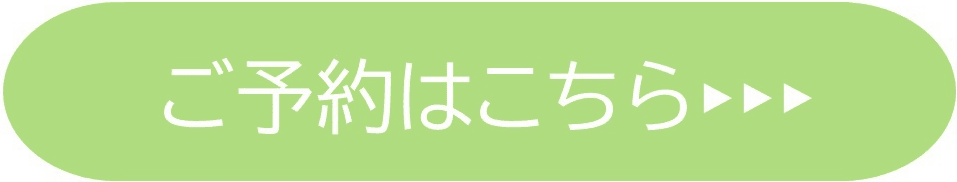ご挨拶
こんにちは。
online相談室ひらり
カウンセラーの平井 葵です。

看護師・保健師・看護教員・お寺の坊守・・・として過ごしてきた中で
本当に多くの方々の相談を受けてきました。
心身の病についてはもちろんのこと
恋愛・結婚・介護・親族とのおつきあい
加えて、相続についてや初心者の投資相談まで!
悩みや抱える問題は百人百様。
そう言っても過言ではありません。
相談してくださる方々にお応えしたい…
この想いでどのようなご相談でも真摯に向き合い
「頑張る」ことをよしとしてきました。
しかし、仕事と家庭の両立ができているつもり…
だったのが、そうではなく
「頑張る」こととは裏腹に
非常にアンバランスであったことに
本当に大切な人を失ってしまう羽目になって
初めて気づきます。
罪悪感、悔恨、怒り、悲哀、恐怖
何よりも強力な自己否定感が
「もう死んだ方がいい」
と思うまでに自分自身を追い込み
これまでの人生のアンバランスさに飲み込まれて
崩れそうでした。
時を経て
死ねなかった自分が生きていくことに何か意味を見出そうと
再び学ぶことを選択します。
数々のセミナーや講義に参加してようやく出会ったメソッド。
本当の気持ちに気づくために、自分自身を見つめるうち
少しづつ何かが「変わってきている」
そういう感覚を味わっていきました。
ー人に良く見られたい
ーできる人だと思われたい
ー認められたい
「人のために役に立ちたい」という気持ちの強さの裏で
過去の経験によって傷ついた私を守ろうとして
強い承認欲求を満足させようと
潜在意識が必死になっていることに気づいたのです。
幼少時に、笑顔を取り上げられた恐怖と
空気を読んで対処しなければつぶれてしまいそうな孤独感
これらを払拭するために
とことん頑張りぬくこと
ー絶対にこうしなきゃ
ーこうあるべき
ー人の見本にならないといけない
ー無駄のない動きをしなきゃ・・・
がんじがらめのルールは
崩れ落ちそうなこの身を
とにかく引き上げようと動いてくれていた
この存在の中にある潜在意識のおかげ・・・
ただ、守られ方が幼いやり方であったばかりに
現実の空回りを引き起こしていた・・・
幼少期からこれまでの体験を掘り起こすことによって
やっとそのことに気づき
少しずつ受け入れることで
ようやく解放されたのです。
両親との関係
幼少期の体験
社会に出てからの生活経験
これまでの人生を作り上げてきたすべての事象は
否定するものではなく
愛すべき大切なエピソードでした。
そして、今となっては
それらのエピソードはすべて幻想である…
つまり、「今」にはない。
そう考えられるようになりました。
肩ひじ張らずに、今、この瞬間を大切にして生きる。
その上で、以前のように
多くの悩みや問題を抱える方々を支えたい。
今では、心からそう思っています。
-1024x681.jpg)